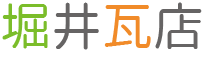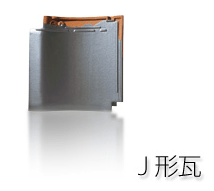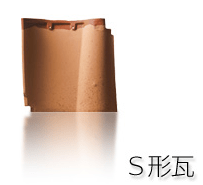【日本の粋】和瓦とは?種類とメンテナンス費用も解説
日本は四季折々の移ろいの中に、日本家屋の瓦屋根が溶け込み美しい風情を漂わせています。
そうした日本風土に合う伝統的な和瓦には、長所がたくさんあります。
現代の日本はたくさんの屋根材が普及しており、それぞれにメリットがありますが、この記事を通じて和瓦の魅力を再発見していただき、また種類による違いや短所、およびメンテナンスと費用について解説していきたいと思います。
和瓦について少しの造詣を深めていただけたらと願っています。
和瓦とは
和瓦は、粘土を練り上げ瓦の形に成型し、乾燥させた後1000~11250℃で焼いた陶器瓦です。
耐久性の高さは抜群で、自然災害などでの破損がなければ、100年以上使用し続けられます。
そして1996年にはJIS(日本工業規格)の改定において、「J形」と名前が取り入れられています。J形瓦の「J」は「Japanese」の頭文字からとられたといわれ、形は緩やかなカーブを描いた日本の代表的な形です。また雨が降った際の水切れもよい瓦です。
和瓦が日本風土にあっていることをよく示していますが、J形瓦は純和風の家だけでなく洋風の家にも使用されるなど、幅広い用途で今なお人気を誇っています。
また和瓦にはさまざまな呼び名があり、「J形」「和形」「和瓦」「日本瓦」とありますが全て同じ瓦のことです。
<引用元:瓦web>
和瓦のサイズ
和瓦(J形瓦)のサイズは、JIS規格で定められており、戸建住宅の場合で30.5cm×30.5cmです。このサイズは1坪に53枚とぴったり合うため、53枚版とも呼ばれています。
そしてこのうち数枚が何等かの都合で割れたとしても、その数枚だけの交換ですみます。
さらに53枚版はAとBという二つの規格があり、Bは少し幅が広くなっています。
なお、53Aは日本の住宅で最もよく使われている三州瓦のサイズで、53Bはその次によく使われる石州瓦のサイズです。
和瓦の重さ
和瓦は重いことで知られています。その重さは1㎡あたり45~50kgで、屋根の面積が100㎡(約30坪)だとした場合じつに5トンにもなります。これは象1頭分が屋根に乗っていることに匹敵します。
ちなみに最近よく使われている防災瓦や軽量瓦は1㎡あたり35kg、スレート瓦(コロニアル屋根)は1㎡あたり20kgですので、和瓦は重さの点では他の屋根材に比べ外壁などに負荷がかかります。
和瓦の製法による種類
和瓦は製法での種類があり、表面の仕上げによって違う「釉薬瓦」と「いぶし瓦」があります。
それぞれの特徴について説明します。
釉薬瓦(ゆうやくかわら)
陶器瓦のことを釉薬瓦(ゆうやくかわら)ともいいます。
瓦の仕上げに釉薬を塗って焼き、釉薬が溶けることでガラス質になり、ツヤがある見た目になり美しさを引き立てます。
またその際に色を付けることもでき、赤茶色や青、緑など住宅の佇まいに合わせた好みの色を着色できます。
現在は釉薬瓦が主流で、色やツヤも長持ちするので喜ばれています。
いぶし瓦
いぶし瓦は、釉薬をかけずに焼いた後、空気を遮断した窯の中でいぶして瓦の表目に炭素の膜を形成します。
炭素の膜は重厚感のある銀色になり、派手さを抑えたお寺や神社、また由緒ある京都の街並みで多く使われています。
いぶし瓦の表面の色は炭素膜の色ですので、年数の経過とともに変化し、屋根に独特の色ムラが生まれてきます。
そうした経年変化も「味がある」趣きを与えるため、いぶし瓦が好まれるいわれとなっています。
日本三大瓦は産地による種類
瓦は、産地による種類分けがされています。
日本三大瓦と呼ばれ、3つの瓦の産地があり三州瓦、石州瓦、淡路瓦を指していますが、みな長い歴史を持っています。
それぞれの特徴を下記に説明します。
三州瓦
三州瓦の生産地は、愛知県西三河、碧南市、高浜市で、日本最高の瓦生産量をもち現在一番使われている瓦です。
製造に際しては1100℃の温度で焼き上げられるため、高い防水性や耐火性があります。
また新しく施工法も工夫され従来の施工法に比べ耐震性・耐風性が飛躍的にアップしています。
また粘土瓦、いぶし瓦、陶器瓦などの種類や、J形以外のデザインの瓦も製造され、豊富なバリエーションや色彩の豊かさが特徴です。
石州瓦
石州瓦は、島根県石見市、江津市、浜田市、益田市、大田市で生産され、主に釉薬瓦が中心で日本第2位の生産力があります。
また1300℃の高温で焼き上げられるため頑丈で塩害に強いことから、寒冷地域や海岸地域で人気です。
赤褐色の瓦が特徴で、見た目も美しく機能性に優れた瓦ですが、価格が他の瓦に比べやや高価です。
淡路瓦
淡路瓦は、その名の通り兵庫県淡路島・南あわじ市で生産されています。
いぶし瓦、陶器瓦、窯変瓦が製造されていますが、いぶし瓦の生産量は日本で第1位です。
淡路瓦の耐圧性による強度は、屋根材に課されるJIS規格よりもはるかに高く、また酸やアルカリによる劣化にも強いため美しい外観が長持ちし、遮音性や遮熱性にも優れています。
和瓦と洋瓦の違いは形状の種類
粘土を高温で焼いた陶器瓦にも洋風の瓦があります。
和瓦は大きく波打った形状をしており重厚感があるのに対し、洋瓦はオレンジやブラウン、紺色など色彩豊かでスタイリッシュな形状をしており、オリジナリティ溢れるおしゃれな印象を与えます。
洋瓦にはS型とF型があり、それらの特徴を説明します。

S型洋瓦
洋瓦のS型瓦の「S」は、「スパニッシュ」の頭文字から由来しています。
大正時代に日本に伝わったとされています。また見た目がS字型に波打っており、和瓦のJ型瓦とは違い立体感のある屋根になり、スペインなど地中海沿岸を思わせる洋風感覚あふれる屋根に葺きあがりお洒落な印象です。
<引用元:瓦web>
F型洋瓦
「F形」のFは、平面を意味するFlat(フラット)から来たという説と、フランス瓦を真似たのでF型になったという説があります。
J形瓦と違い山と谷のデコボコなくした洗練された平板状のデザインで、平板瓦(へいばんがわら) とも呼ばれます。
現在もっともよく使われているのが平板瓦と呼ばれるタイプで、洋風住宅のみならず和風住宅でも使われています。
陶器瓦の特色である美しい色彩と耐久性の高さを持ち、総合的にみてバランスのいい屋根材として人気です。
施工は比較的容易なため、短期間で屋根工事を済ませたい人に適しています。

<引用元:瓦web>
和瓦の魅力となる長所
日本伝統の和瓦には、見た目の重厚感だけでなく素材に関する長所がたくさんあり、魅力を再発見できます。
下記に7つの長所について説明します。
| 1.耐火性能 2.耐水性能 3.耐寒性能 4.断熱性能 5.防音・快適性能 6.耐久性 7.耐震性 |
1.耐火性能
江戸時代は火事が多くて有名だったことは知られています。 当時、瓦のない板葺きの屋根が使われていたため、屋根の上に火の粉がかかると火はあっという間に燃え広がりました。そうした 火事の被害を減らすために瓦が使われだしたといわれています。
この事例から瓦には耐火性能が重要となることがわかります。
1100度以上の高温で焼き上げられる瓦は、建築基準法指定の安全な不燃材で、火事を屋根から類焼するのを防ぎます。
※建築基準法(平成16年9月29 日国土交通省告示第1178号)
2.耐水性能
耐水性は屋根材の必須条件のひとつです。
なぜなら日本の平均の年間降水量は1,500mm~2,000mmで、降水量の多い地域では4,500mm以上にも達するからです。
瓦は茶話や皿と同様の陶器質で水を通しません。さらに陶器質の滑らかさは瓦表面の雨走りを良くし、瓦の形状も雨を早く流し落とすようデザインされています。
また瓦だけでなく屋根下地などにも屋根全体に耐水設計・耐水工法がなされており、耐水性能は万全といえるでしょう。
3.耐寒性能
屋根が氷点下になる地方もある日本では、耐寒性能も重要な要素です。
水分が凍結することで瓦にヒビが入ったり割れたりすることがないことが必要です。
瓦屋根は凍結に強い耐寒性で、寒冷地でも広く取り入れられています。
4.断熱性能
屋根材は灼熱の夏の高温、凍える真冬の寒気にさらされるため、屋外の温度から屋内を守る遮断性能が必要です。
和瓦の形には通気性を促し断熱性を高めるようにできています。つまり波うつようなカーブの空間に空気が入ることで、自然な通気性ができるのです。
また屋根下地の断熱材施工は、室内の温度を快適に保ち日本に四季に応じた住環境を守ります。
5.防音・快適性能
屋根は激しくたたく雨音の騒音が問題となりますが、瓦は防音性能に優れ、そうした外部からの騒音をシャットアウトし静かな暮らしを約束してくれます。
赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭には適した屋根材といえるでしょう。
また和瓦は快適性にも富み、他の屋根材に比べ夏は涼しく冬は暖かいことも知られています。日本の四季の変化に合わせて快適に過ごせます。
6.耐久性
和瓦の長所の最大の長所は耐久性です。奈良市にある元興寺(がんごうじ)には飛鳥時代に創建され、当時の軒平瓦が今も使われています。1400年の時を経て破損もないことから、和瓦の高い耐久性を証明しています。
現在も耐久年数は100年以上と言われるほど高く、また和瓦そのものに関してはメンテナンスは不要です。
7.耐震性
全国陶器瓦工業組合連合会によれば、2001年策定の工法で施工されていれば、瓦屋根でも震度7クラスの大地震でも安全であると検証されています。
重い屋根は地震に不利と言われていますが、2016年4月の熊本地震で倒壊した住宅には、軽い屋根材が使われていても、住宅全体の耐震性能が低いと倒壊していました。
耐震補強は屋根の重さよりも建物の壁量を増やすことが有効とされています。
瓦屋根の耐震性を知る

和瓦の短所
建築基準法では瓦の種類によって最低勾配が定められ、4寸勾配(約122mm・約21.8゜)が最低勾配に指定され傾斜角度がきつく設定されています。その勾配では雨漏り等はしにくくなるのですが、勾配がきついと屋根足場が必要になるため施工費用が高くなってきます。
価格が割高で専門技術が必要
和瓦は屋根材としては価格が割高になります。近年よく使用されているスレート瓦と比較すると2倍ほどの価格差が生じます。
また和瓦の設置には専門技術が必要で、手作業での施工になり業者選びが課題となってきます。
重さ
瓦屋根のデメリットはやはり重さになります。
陶器なので重量があるため、建物も瓦の重さに耐える構造が必要で、建築費も割高になってきます。
また地震による倒壊は構造に問題があるとしても、屋根は軽ければ軽いほど揺れは少なるなる傾向は無視できません。
和瓦のメンテナンス
和瓦の点検ポイントは4つあります。
| 1.棟瓦の歪み 2.瓦のずれ、割れ、欠け 3.漆喰 4.防水紙、野地板 |
では詳しく説明します。
1.棟瓦の歪み
瓦屋根の頂点にある棟瓦が、歪みなく一直線に並んでいる必要があります。
瓦を支える漆喰の劣化で棟瓦の歪みが生じ、放っておくと屋根が崩れてしまいます。
台風後に被害が出やすいので、一度点検を行うことをおすすめします。
2.瓦のずれ、割れ、欠け
和瓦は頑丈でちょっとしたくらいでは割れませんが、強風で大き目のな看板が飛んできて瓦にぶつかったり、アンテナが倒れた衝撃で瓦が割れたり、ずれたり欠けたりします。
そのままにしておくと割れた部分から雨水が入り防水紙やその下の野地板の劣化を招き、雨漏りの原因となります。
ですから台風などで物が飛んできた形跡がある場合は、早めに瓦の破損個所を発見し素早い補修が必要です。
破損した瓦は1枚からでも交換できます。

3.漆喰
瓦と瓦の間を埋めているのが漆喰です。経年劣化で崩れや剥がれが生じると、瓦を支える力が弱くなり、前述しましたが棟瓦の歪みに繋がります。
瓦そのものは50年以上持つのですが、漆喰の耐用年数は20年くらいですので、瓦自体が何もなくても20年が過ぎたら、一度点検してみることが望ましいでしょう。
4.防水紙、野地板
外側から見えない部分で屋根にとっては非常に重要な部分に、瓦の下の防水紙、屋根を支える木材である野地板があります。
瓦自体には何もなくても、先ほどの漆喰と同じように防水紙や野地板が傷んできてしまいます。
おおよそ30年が過ぎたら張り替えなどのリフォームが必要です。
和瓦のメンテナンス費用相場
場所によって異なる価格の相場をまとめました。
内 容 価 格 瓦の交換 1~5万円/枚 漆喰補修 2,200~7,000円/m 葺き直し(締め直し) 10,000~18,000円/m 葺き替え 100~200万円
<引用元:ユーコーナビ>
足場の設置が必要になればこれに15~20万円程度が加算されます。
まとめ
和瓦は日本風土にあった機能性を持っています。丈夫さと耐久性は歴史的建造物からも明らかです。
他にも和瓦の良さはたくさんあり、近年使われている屋根素材にも引けを取らなかったことでしょう。
この記事を通じ、和瓦の種類や長所・短所、メンテナンスの項目や費用について、和瓦全体の知識も深まったことと思います。
意外にも地震にも強いことは目から鱗の発見でした。
さらに和瓦は初期費用こそ高いですが、メンテナンスや点検はそんなに必要ではなかったので、低コストといえるかもしれませんね。
この記事を通じ、日本伝統の粋が集まった和瓦の魅力を再発見していただき、今後の屋根選びや豊かな知識への参考にしていただければと願っています。