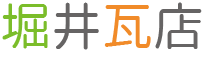瓦屋根のDIY修理はどこまで可能?安全な応急処置と避けるべき症状・注意点を解説
台風が去った後、瓦の少しのズレやひび割れなどを見つけると、これくらいなら自分で直せるのではとDIYを考える方もおられるかもしれません。
しかし、屋根の上の作業は素人では想像できない危険が潜んでいる上、安易なDIYによって修理がさらに必要になることがあります。
そこでこの記事は、DIYでも可能な修理範囲と具体的な方法、DIYを絶対に避けるべき症状などを解説します。
屋根修理に関して正しい知識を持ち安全に対処し、プロに任せるべき点は迷わず相談するための参考にしていただければと願っています。
瓦屋根の損傷でDIYは可能か?判断の目安
屋根の上の作業は、ちょっとした一般的なDIYとは危険性のレベルで大きな違いがあります。
屋根のDIYが可能かどうか判断するため、目安となる要素を3つ解説します。
高所作業の危険性を認識
住宅の屋根でも、高さは2~3メートル以上あり、足を踏み外せば命にかかわる重大事故につながります。
また屋根によって傾斜がきつい場合や、台風の雨で湿った状況は特に滑りやすく、プロの職人でも命を落とすほど危険です。
また屋根付近の電線接触による感電事故も報告されています。
こうした理由で、基本的に素人による屋根のDIYは勧められていません。
DIYの補修は応急処置のみ
屋根のDIYは、あくまで一時的な応急処置に限定されます。
なぜなら、瓦のひび割れやズレをDIYで固定できても、根本的な原因が解決されていないことがほとんどだからです。
ですから、応急処置を行った後には、必ず屋根の専門業者に点検を依頼し、問題がないか確認してもらうことが重要です。
火災保険や助成金の活用も検討
台風などの自然災害で屋根瓦が損傷すると、火災保険が適用されるケースがあります。
しかし、DIYで修理を行ってしまうと火災保険で補償されない可能性があるため、修理を着手する前に保険会社にどこまでのDIYなら適用されるか確認が必要です。
また、適用される場合でも、被害直後に行った応急処置の写真を残しておくと有利に申請を進められるでしょう。
さらに、破損具合によって国や都道府県から助成金が支給される場合もありますので、自治体に問い合わせてください。
DIYが可能なケース
DIYで応急処置が可能なケースとは、あくまでごく軽微な損傷であり安全が確保されている場合に限られます。
DIY可能な損傷の範囲
以下の条件に当てはまる場合、DIYでの応急処置が可能な範囲とみなされます。
- 瓦の割れが軽微で、枚数が少ない場合(数枚程度)。
- 瓦が少しだけずれている場合。
- 雨漏りが発生していない場合。雨漏りしている場合は業者に相談が必要です。
- 下地(防水紙や野地板など)に影響がない場合。
- 築20年以上経過した日本瓦の部分的な交換。洋瓦の交換は難しいため推奨されません。
- 屋根仕事に慣れていて、安全が確保できる場合。
具体的な応急処置の方法
DIYができる場合の具体的な応急処置の方法を紹介します。
防水テープによる補修
小さなひび割れの際には、水の侵入を一時的に防ぐのに有効です。
1. 割れた瓦を一旦撤去:周囲の瓦を傷つけないよう注意し、屋根上を歩く際は必ず瓦の谷部分を縦に踏む。
2. 貼る箇所の清掃: 雑巾で汚れや水気を除去し、綺麗にする。油汚れはアルコールで拭くと良い。
3. 防水テープを貼る: 割れた瓦にテープを貼り、元の形に戻す。補強のため2~3度重ねて貼ると良い。
4. 下地の確認: 野地板に破損がないか確認し、破損があれば塞ぐ。
5. 瓦を戻す: 瓦を元の位置に戻し、周辺の瓦をずらさないよう注意する。
パテによる補修
防水テープよりも強度を上げて補修したい場合に行います。
- 貼る箇所の清掃: 汚れや水気を除去する。
- パテを塗る: 割れた箇所がしっかりと埋まるようにパテを塗り込み、瓦が元の形に戻るようしっかり押さえる。
- 余分なパテを拭き取る:はみ出した部分は雑巾やヘラで拭き取り、中に押し込む。
- 表面を滑らかに整える:ヘラやヤスリで凹凸を滑らかにする。
- ガルバリウム鋼板で補強:瓦より小さめにカットし、瓦の山と谷に沿って折り曲げたガルバリウム鋼板を、瓦の裏からあてて差し込む。曲げ度合いを誤ると形が崩れるため丁寧に行う。
- 瓦を戻す: パテで補修した瓦を元の位置に戻す。瓦の下の汚れや劣化がないか確認し、あれば掃除してから戻す。
ずれた瓦の調整
軽度の瓦のずれなら調整できますが、高所の作業ですので安全を十分確保してください。
- ずれている瓦を見極める。
- 瓦専用のハンマーでコツコツと叩いて位置を調整する。
力を入れすぎると瓦が割れてしまうため、力加減に注意してください。
DIYを行う際の注意点と安全対策

瓦屋根のDIYは、高所における作業であることが最大の注意点です。
その点を踏まえて以下の点を考慮して行いましょう。
高所作業における安全確保
• 必ず2人以上で作業する:万が一の事態に備え、はしごを支える人と屋根に上る人の役割分担のため最低でも2人必要です。
• 安全装備の着用:ヘルメットと安全帯(フルハーネス)は必須です。
高所作業での安全装備は法律で義務付けられています。
安全帯に慣れていないと転倒する可能性もあるため、地上で練習しておきましょう。
• 天候に注意:雨上がりや強風の日は絶対に作業を行わないでください。
特に釉薬瓦は濡れると非常に滑りやすく危険が増します。また、熱中症のリスクも考慮しましょう。
• 足場設置の検討:高所作業での転落リスクを大きく下げるため、足場だけでも業者に依頼する選択肢も有効です。
屋根の上を歩く際の基本ルール
• 瓦の谷の部分を縦に踏む:瓦の山や横を踏むと瓦が割れやすいため、必ず谷部分を縦に踏みましょう。
• 外した瓦の下は丁寧に掃除する:ホコリや雨水が溜まっていると、屋根材や防水シート(ルーフィング)の劣化してしまいます。また劣化がないか確認しながら丁寧に掃除してください。
「やってはいけない」こと
DIYでやり方を誤ると、かえって状況を悪化させてしまいます。
やってはならないことに注意しましょう。
• 釘を打たない:素人考えで瓦の固定のために釘を打ってしまうと、瓦が割れたり打った部分から雨水が侵入する危険がありますからやめましょう。
瓦の固定は釘を打ちつけませんので注意してください。
セメントは使用しない:セメントは瓦を強く固めすぎてしまうため、あとで業者が修理しようとすると瓦を割ってしまう原因になります。また、プロの瓦屋根工事ではセメントは使いません。
• むやみにコーキング材で隙間を塞がない:瓦同士の隙間は雨水の排水経路となり雨漏りを防いでいます。隙間を全て埋めてしまうと雨水が排出されなくなり、雨漏りを誘発し下地の野地板が腐食する原因となります。
• 軒先を塞がない:雨水が流れる方向(水下側)の排水経路を塞ぐと、雨漏りを悪化させるため絶対に行ってはいけません。
DIY後に必ず行うべきこと
DIYでの補修はあくまで応急処置です。必ず専門業者に点検してもらい、問題がないか確認してもらうことが大切です。
DIYで安く上げようと自分で修理すると、危険が伴うだけでなく、かえって損傷を大きくする場合があります。
また、DIY後にプロの点検が必要になることを考えれば、あくまで応急処置だけに限定し、プロに任せる方が確実でトータルすると安価に済むかもしれませんね
DIYを避けるべき症状と状況

以下の症状や状況が見られる場合は、DIYではなく必ず専門業者に依頼してください。
無理なDIYは、状況を悪化させるだけでなく、高額な修理費用に繋がるでしょう。
雨漏りが発生している場合
雨漏りの原因は、瓦そのものより下地の防水シートや野地板にあることが多く、原因箇所を特定するのは困難です。
雨漏りの根本原因が解決されないと再発することが多く、原因を探るために専門的な調査が必要とされています。
雨漏りの症状がある場合は、防水テープなどの応急処置にとどめ、本格的な修理は業者に依頼しましょう
瓦の不具合が屋根全体に及ぶ場合
数枚の瓦の不具合であればDIYも可能かもしれませんが、広範囲の損傷や複数の瓦のズレ・落下(3枚以上)はDIYの範囲ではありません。
素人が瓦を積み直すと、瓦の重なりが揃わず暴風で一気に飛散するリスクもあります。
災害に便乗する悪質業者に要注意
災害後にあちらこちらで出現する「屋根瓦が割れていますよ」などと突然訪問してくる業者は、悪徳業者の可能性が高いので注意してください。
優良業者は災害後は依頼が殺到し、多忙を極めているはずですので直接訪ねてまで仕事を取る必要はありません。
また、「近くで工事をしているので、ついでに修理しますよ」といった営業も、相手都合であり避けるべきです。
悪質な業者による被害を避けるためには、すぐに契約しないことを鉄則としましょう。
もし契約してしまった場合は、訪問販売の際は8日以内であればクーリングオフが可能です。
さらに興味深いことに、普通の訪問販売業者に突然勧誘されて契約・工事をされたケースでは、 工事完了後でも8日以内ならクーリングオフ可能 なので覚えておきましょう。
たとえ、業者が「もう工事したから無理」と言っても、正式な契約内容の書面を受け取った8日以内なら契約解除可能です。
これは「特定商取引法第9条第1項」に基づく消費者保護の制度で、理由を問わず無条件で契約を解除できるのが特徴です。
まとめ
瓦屋根のDIY修理は、軽微な割れやずれに対する防水テープ・パテでの応急処置などに限って行うのが賢明です。
応急処置でDIYを行う際は、屋根は高所作業で非常に危険であり、滑って落下するリスクが常にあることを念頭におく必要があります。
また素人判断で間違うと修理箇所が悪化しますし、火災保険の適用が受けられなくなること周知しておきましょう。
プロに頼むなら、徹底した安全対策を施し、根本的な修理を行い長期的な安心も得られます。
悪徳業者に注意し、無料点検や相見積もりで信頼できる業者を選び、大事な資産であるお住まいを守ってください。